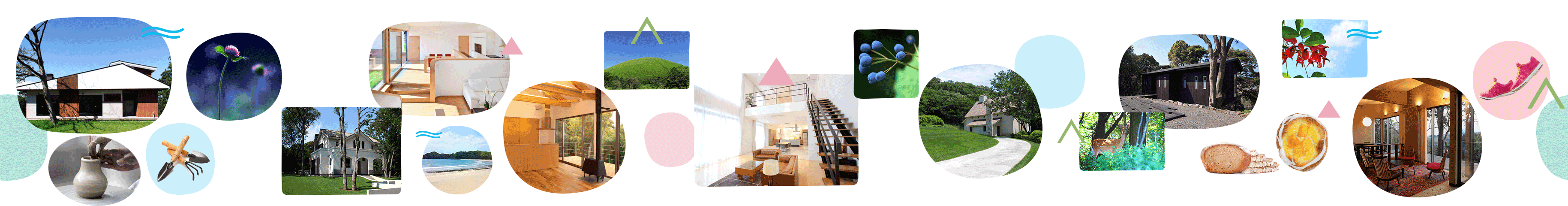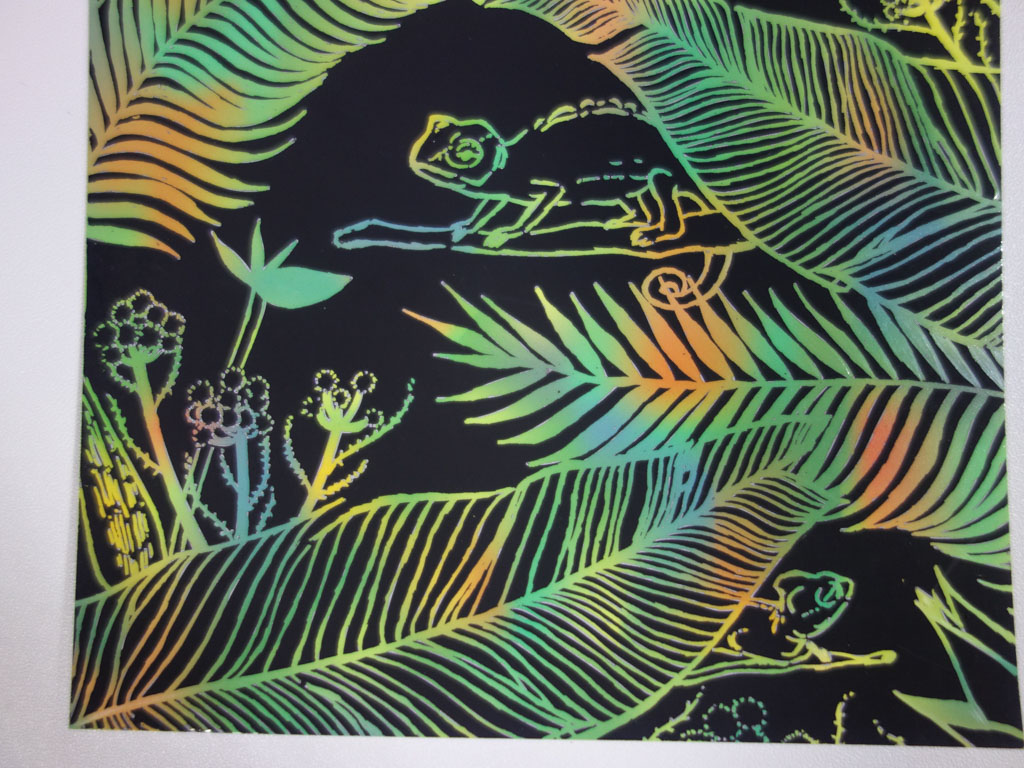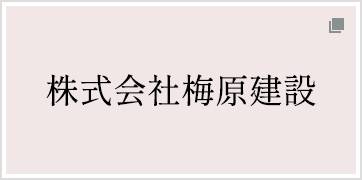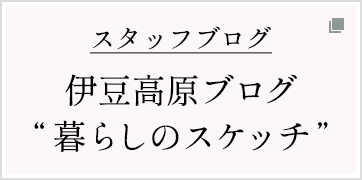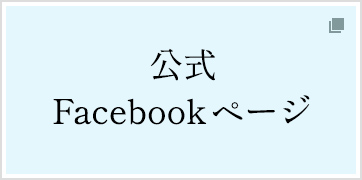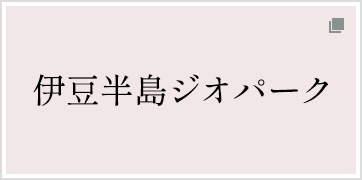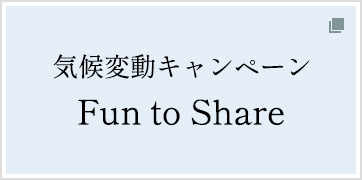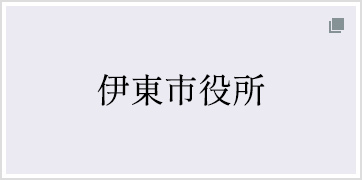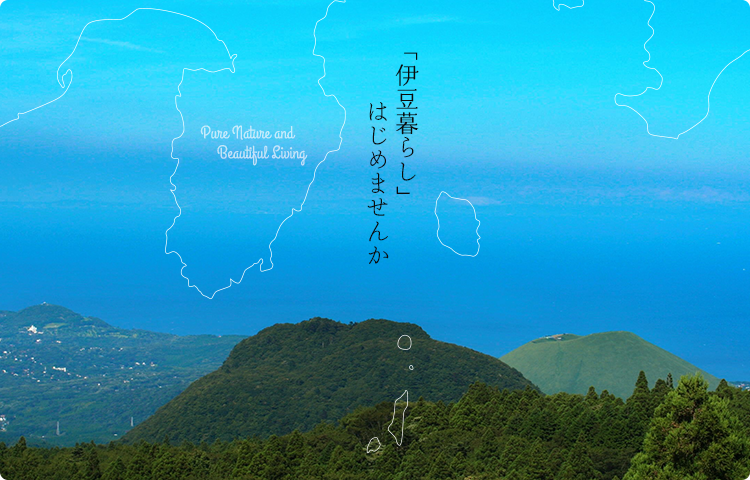
おすすめ物件RECOMMEND
- NEWNo.6527

大川~白田エリア
680万円
6527:海を見ながら家庭菜園を楽しめる2SLDK
- 最寄り駅
- 伊豆熱川
- 交通
- 伊豆急行線 伊豆熱川駅より3km 車約5分
- 土地面積
- 401㎡(121坪)
- 建物面積
- 90㎡(27坪)
詳しく見る
- NEWNo.6518

川奈~富戸エリア
980万円
6518:緑に包まれた静かな環境に佇む2LDK+4S
- 最寄り駅
- 川奈
- 交通
- 伊豆急行線 川奈駅より5.2km 車約9分
- 土地面積
- 1,382㎡(418坪)
- 建物面積
- 58㎡(17坪)
詳しく見る
- NEWNo.6531

宇佐美~伊東エリア
1,180万円
6531:市街地の夜景や海を望む伝統的な和風建築住宅3LDK
- 最寄り駅
- 南伊東
- 交通
- 伊豆急行線 南伊東駅より5.4km 車約9分
- 土地面積
- 287㎡(86坪)
- 建物面積
- 107㎡(32坪)
詳しく見る
- NEWNo.6538

大川~白田エリア
1,280万円
6538:自家菜園やガーデニングを楽しめる2LDK
- 最寄り駅
- 伊豆熱川
- 交通
- 伊豆急行線 伊豆熱川駅より4.7km 車約8分
- 土地面積
- 832㎡(251坪)
- 建物面積
- 87㎡(26坪)
詳しく見る
- No.6491

川奈~富戸エリア
1,480万円
6491:徒歩圏内に生活利便が整う使い易い平屋建て4LDK
- 最寄り駅
- 川奈
- 交通
- 伊豆急行線 川奈駅より2.7km 車約5分
- 土地面積
- 663㎡(200坪)
- 建物面積
- 100㎡(30坪)
詳しく見る
- NEWNo.6102

城ヶ崎~伊豆高原エリア
1,780万円
6102:海と伊豆大島を正面に望む3SLDK
- 最寄り駅
- 伊豆高原
- 交通
- 伊豆急行線 伊豆高原駅より7.8km 車約13分
- 土地面積
- 384㎡(116坪)
- 建物面積
- 146㎡(44坪)
詳しく見る
- No.6343

川奈~富戸エリア
1,800万円
6343:自然豊かな231坪の敷地に佇む平屋建て2LDK・吹抜けのリビングが開放的で魅力です
- 最寄り駅
- 川奈
- 交通
- 伊豆急行線 川奈駅より5.5km 車約10分
- 土地面積
- 765㎡(231坪)
- 建物面積
- 76㎡(23坪)
詳しく見る
- No.6504

城ヶ崎~伊豆高原エリア
1,880万円
6504:令和4年3月にリフォーム済、伝統とモダンが融合する4SLDK
- 最寄り駅
- 伊豆高原
- 交通
- 伊豆急行線 伊豆高原駅より5km 車約9分
- 土地面積
- 468㎡(141坪)
- 建物面積
- 151㎡(45坪)
詳しく見る
- DOWNNo.6260

城ヶ崎~伊豆高原エリア
1,960万円
6260:伊豆の海や島々を望む開放的なロケーション・各居室広々とした4SLDK
- 最寄り駅
- 伊豆高原
- 交通
- 伊豆急行線 伊豆高原駅より5.3km 車約9分
- 土地面積
- 417㎡(126坪)
- 建物面積
- 104㎡(31坪)
詳しく見る
- NEWNo.6546

城ヶ崎~伊豆高原エリア
2,150万円
6546:陽当たりの良い北東角地・海を望む4LDK+2S
- 最寄り駅
- 伊豆高原
- 交通
- 伊豆急行線 伊豆高原駅より1.6km 徒歩約20分
- 土地面積
- 480㎡(145坪)
- 建物面積
- 142㎡(43坪)
詳しく見る
- NEWNo.6532

城ヶ崎~伊豆高原エリア
2,180万円
6532:桜並木通りに近く、お庭を楽しむ和風3SLDK
- 最寄り駅
- 伊豆高原
- 交通
- 伊豆急行線 伊豆高原駅より2.4km 徒歩約30分
- 土地面積
- 537㎡(162坪)
- 建物面積
- 98㎡(29坪)
詳しく見る
- No.6378

城ヶ崎~伊豆高原エリア
2,480万円
6378:城ヶ崎海岸駅へ歩ける、海を望む温泉付きの2LDK+1DK
- 最寄り駅
- 城ヶ崎海岸
- 交通
- 伊豆急行線 城ヶ崎海岸駅より600m 徒歩約8分
- 土地面積
- 452㎡(136坪)
- 建物面積
- 66㎡(20坪)
詳しく見る
- NEWNo.6497


川奈~富戸エリア
2,580万円 (税込)
6497:約320坪の広々とした敷地・令和6年3月リフォーム済みの山荘風平屋建て3LDK
- 最寄り駅
- 川奈
- 交通
- 伊豆急行線 川奈駅より4.7km 車約8分
- 土地面積
- 1,059㎡(320坪)
- 建物面積
- 90㎡(27坪)
詳しく見る
- No.6429

城ヶ崎~伊豆高原エリア
2,980万円
6429:小川のせせらぎを楽しむ4SLDK
- 最寄り駅
- 伊豆高原
- 交通
- 伊豆急行線 伊豆高原駅より1.7km 徒歩約22分
- 土地面積
- 623㎡(188坪)
- 建物面積
- 108㎡(32坪)
詳しく見る
- NEWNo.6529

城ヶ崎~伊豆高原エリア
3,360万円
6529:平成24年築の上品なモダン住宅3SLDK
- 最寄り駅
- 伊豆高原
- 交通
- 伊豆急行線 伊豆高原駅より2.5km 車約5分
- 土地面積
- 667㎡(201坪)
- 建物面積
- 99㎡(30坪)
詳しく見る
- No.6453

城ヶ崎~伊豆高原エリア
3,380万円 (税込)
6453:南西角地の高台に建つ新築2LDK+2S
- 最寄り駅
- 伊豆高原
- 交通
- 伊豆急行線 伊豆高原駅より3.1km 車約6分
- 土地面積
- 493㎡(149坪)
- 建物面積
- 83㎡(25坪)
詳しく見る
- DOWNNo.6418

城ヶ崎~伊豆高原エリア
3,460万円 (税込)
6418:海と山並みを望む・吹き抜けリビングが開放的な新築和モダン3SLDK
- 最寄り駅
- 伊豆高原
- 交通
- 伊豆急行線 伊豆高原駅より2.2km 徒歩約28分
- 土地面積
- 380㎡(114坪)
- 建物面積
- 112㎡(33坪)
詳しく見る
- No.5930

城ヶ崎~伊豆高原エリア
3,490万円
5930:平成28年内外装フルリフォームを施した3LDK
- 最寄り駅
- 城ヶ崎海岸
- 交通
- 伊豆急行線 城ヶ崎海岸駅より1.2km 徒歩約15分
- 土地面積
- 530㎡(160坪)
- 建物面積
- 144㎡(43坪)
詳しく見る
- NEWNo.6519

大川~白田エリア
3,950万円
6519:伊豆七島を一望できる ガレージ・露天風呂付きセキスイハウス施工2LDK+3S
- 最寄り駅
- 伊豆熱川
- 交通
- 伊豆急行線 伊豆熱川駅より4.2km 車約7分
- 土地面積
- 917㎡(277坪)
- 建物面積
- 155㎡(46坪)
詳しく見る
- NEWNo.6496

城ヶ崎~伊豆高原エリア
4,100万円
6496:スーパー・郵便局近く、利便性の良い住環境・広々ウッドデッキの大型5SLDK
- 最寄り駅
- 伊豆高原
- 交通
- 伊豆急行線 伊豆高原駅より850m 徒歩約11分
- 土地面積
- 1,005㎡(304坪)
- 建物面積
- 166㎡(50坪)
詳しく見る
- No.6478

宇佐美~伊東エリア
4,880万円
6478:伊東市街地の夜景と海を望む、平成24年築・地元工務店施工3LDK
- 最寄り駅
- 伊東
- 交通
- 伊豆急行線 伊東駅より2.1km 徒歩約27分
- 土地面積
- 793㎡(240坪)
- 建物面積
- 123㎡(37坪)
詳しく見る
- NEWNo.6441


城ヶ崎~伊豆高原エリア
5,950万円 (税込)
6441:佐藤秀のデザイン施工・拘りを貫いたビルドインガレージ付きの本格和風建築6LDK
- 最寄り駅
- 伊豆高原
- 交通
- 伊豆急行線 伊豆高原駅より2.4km 徒歩約30分
- 土地面積
- 654㎡(197坪)
- 建物面積
- 260㎡(78坪)
詳しく見る
- No.6400

大川~白田エリア
6,500万円
6400:海を一望するハイグレードな洋風住宅で伊豆暮らし
- 最寄り駅
- 伊豆熱川
- 交通
- 伊豆急行線 伊豆熱川駅より3.9km 車約7分
- 土地面積
- 1,204㎡(364坪)
- 建物面積
- 151㎡(45坪)
詳しく見る
- No.6230

城ヶ崎~伊豆高原エリア
6,900万円
6230:海を望む平成17年築の宿泊施設は各客室に浴室を完備しています
- 最寄り駅
- 伊豆高原
- 交通
- 伊豆急行線 伊豆高原駅より4.3km 車約8分
- 土地面積
- 935㎡(282坪)
- 建物面積
- 301㎡(91坪)
詳しく見る
物件更新情報(4/25更新)
- 4/25予約6386:森林の中、静かに佇む薪ストーブ付きスウェーデンハウス3LDK
- 4/25成約5942:平成19年築の温泉付きの2LDKは高台より海を望みます
- 4/25予約6427:国産の檜や杉をふんだんに使用した瓦屋根の和風建築2LDK
- 4/22新規6546:陽当たりの良い北東角地・海を望む4LDK+2S
- 4/21値下6339:天井の高いリビングと対面キッチンが魅力・海を望むオール電化の未入居2SLDK
- 4/21値下6459:城ヶ崎海岸駅より950m・国道へのアクセスの良い新築2SLDK
- 4/21値下6533:桜並木通り近くに位置する海を望む新築2LDK+3S
- 4/20成約6513:令和6年1月内外装リフォーム・広々とした芝庭と水屋付きの平屋建て
- 4/20成約6396:敷地面積630坪の元保養所跡地・伊豆大島を望む温泉権利付き平坦地
- 4/19値下3874:豊かな緑に囲まれたプライベート感のある住環境
- 4/19成約6479:伊豆大島や入江を雄大に望む・令和6年3月リフォーム済み2SLDK
- 4/19成約6524:城ヶ崎海岸桜並木通りに面したモダンな洋風住宅は3LDK+2S
- 4/19値下6267:令和4年内外装リフォーム済み・中庭のある和風平屋建て3DK
- 4/18予約6501:伊豆高原駅より1.1kmの好立地に建つ3LDK平屋建て
- 4/15成約6530:海を望む薪ストーブ付きの吹抜けリビング3LDK
- 4/13値下6418:海と山並みを望む・吹き抜けリビングが開放的な新築和モダン3SLDK
- 4/13値下6306:ゆとりある56坪の建物は4LDK+2S・2台分のガレージ付きが魅力です
- 4/13値下5783:南道路で陽当り良好な土地
- 4/13値下6260:伊豆の海や島々を望む開放的なロケーション・各居室広々とした4SLDK
- 4/13値下6251:海を望む温泉付き2SLDK+サンルーム
- 4/12成約6528:高台より眼下に海や島々を望む・三面採光のリビングが開放的な平屋建て
- 4/12新規6538:自家菜園やガーデニングを楽しめる2LDK
- 4/11値下6390:約304坪の広い敷地が暮らしを彩る・夜景や花火を楽しむリフォーム済み3LDK
- 4/8予約5799:城ヶ崎海岸駅まで約450mの高台で平坦な土地
- 4/8成約6472:伊豆大島を望む平成23年築、地元工務店施工3LDK+2S
- 4/8成約6466:令和5年12月リフォーム済み・桜並木通りと海を眺める高台に建つ3LDK
- 4/8値下6489:小川のせせらぎが聞こえる、森の中の高床式山荘風4SLDK
- 4/7値下6152:ドッグランに最適・227坪の敷地に建つハワイアンブルーのリゾートハウス2LDK
- 4/7予約6537:サウナと温泉、暖炉が演出する贅沢な伊豆暮らしを実現する2LDK+2Sのデザイン住宅
- 4/6値下6453:南西角地の高台に建つ新築2LDK+2S
- 4/4予約6351:入江や半島を眼下に望む・建物はレンガ張りで重厚感のある鉄筋コンクリート造りの大型6DK
- 3/30値下6252:手入れの良い平坦なお庭付き・南欧風3LDK
- 3/30値下6510:城ヶ崎海岸駅より約800mの平屋建て2DK
- 3/29新規6532:桜並木通りに近く、お庭を楽しむ和風3SLDK
- 3/28値下6474:雄大な景色とゆとりの間取りロワジール伊豆高原壱番館
小冊子のお届け「Maple Express」
メープルニュース(update: 4/25)
「伊豆暮らし」を
始めるための
ガイドブック
永年に渡り伊豆高原のリゾート物件を取り扱ってきたメープルハウジングだからこそお届けできる、一歩進んだ「伊豆暮らし」の成功の秘訣をご紹介いたします。
伊豆スタイル
洗練された暮らしがみずみずしい自然の中にとけあう伊豆別荘でのリゾートライフ。アート・ショップ・イベントなど、上質な衣・食・住の情報を満載でご紹介いたします。